神具
2013年10月28日 by sporder ブログNo.1177
ブログNo.1177
ふとん太鼓のとんぼ(屋根の白い飾り)
ふとん太鼓の屋根の最上部四隅に飾るとんぼ(白飾り)を製作しました。
神社の御造営にあわせて新調されます。
現状の寸法どおり、全長160㎝、直径5㎝、で仕上げております。
結びの形はお見本どおり8の字で、
先端が長く出るように結びあげております。
とんぼの形は 一様でなく、地域によって継承された様々な形があります。


カテゴリー: 神具, 祭具, 御輿 | コメントは受け付けていません。
2013年10月26日 by sporder ブログNo.1175
ブログNo.1175
揚巻房 赤 1尺
揚巻房を製作しました。
房の長さが1尺(約30cm)の大型の房です。
仕様は、 赤色の平頭のより房です。
社紋が染め抜かれた紫地の幕の中心が、
赤色の揚巻房で引き上げれて、
神前幕の設えが完成します。


カテゴリー: 神具, 祭具 | コメントは受け付けていません。
2013年10月24日 by sporder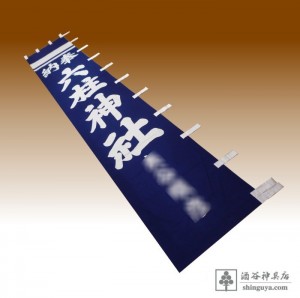 ブログNo.1173
ブログNo.1173
幟 71×410cm 綿厚地
幟を製作しました。
全長410cm、幅71cm、生地は綿厚地、
濃紺地に社名と奉納者名を白で染め抜いています。
最上部の二本のラインも継承された形です。

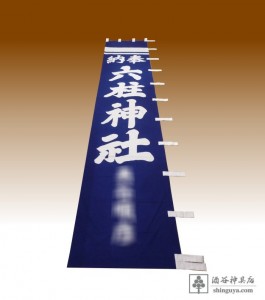
カテゴリー: 神具, 祭具 | コメントは受け付けていません。
2013年10月22日 by sporder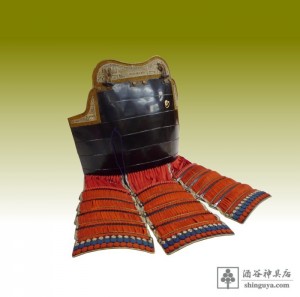 ブログNo.1172
ブログNo.1172
鎧修理 揺らぎ糸取替え、胴塗り替え
鎧を修理しました。
長年のご使用で、草摺(くさずり)と胴をつなぐ
揺らぎ糸が擦り切れておりましたので、
現状の糸に色を合わせて、
揺らぎ糸をお取替えしました。
胴部分も黒色で塗り替えております。
兜の立物の新調(ブログNo.1170)と合わせて、
鎧兜の修理が完成しました。


カテゴリー: 神具, 祭具, 修理・修復 | コメントは受け付けていません。
2013年10月20日 by sporder ブログNo.1170
ブログNo.1170
立物を新調しました。
秋の祭典に着用される兜の立物で、
紋は社紋の左三つ巴です。
専門の錺り金具職人の手によって製作された立物は、
直径9cm、厚み1cm、
本金鍍金で仕上げております。
兜の中心に納まった三つ巴の社紋が、
品良く輝いています。


カテゴリー: 神具, 祭具, 装束類 | コメントは受け付けていません。
2013年10月18日 by sporder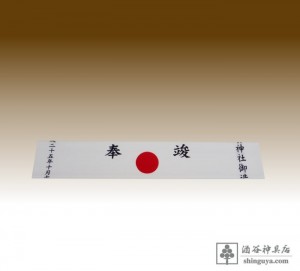 ブログNo.1170
ブログNo.1170
鉢巻 社名、日の丸入り
鉢巻を製作しました。
御造営の祭典当日、
お神輿を担ぐ氏子様が、頭に巻かれます。
全長90cm、幅36cm
中心に日の丸、上部に『奉竣』、左右に、社名・年月日を入れております。
日の丸の配置は、三つに折りたたんだときに、
文字と日の丸とのバランスを取れるように配しております。
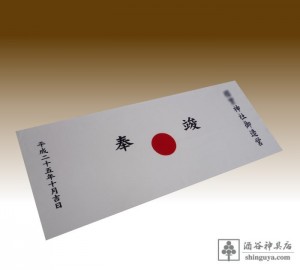
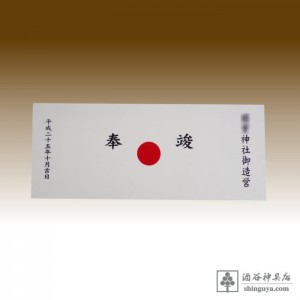
カテゴリー: 神具, 祭具, 装束類 | コメントは受け付けていません。
2013年10月15日 by sporder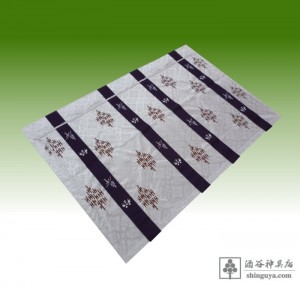 ブログNo.1167
ブログNo.1167
壁代 人絹緞子 白地 布筋紫
壁代をお仕立てしました。
神殿の御社内側面三面に設えられます。
幅 89cm、丈59cm、
生地は白地の人絹緞子です。
布筋は側面の中心に1本づつ、
後ろ面に2本の計4本配しております。


カテゴリー: 神具, 祭具 | コメントは受け付けていません。
2013年10月13日 by sporder ブログNo.1165
ブログNo.1165
円座 渦巻き 2尺2寸
円座を製作しました。
板張りの神殿内上段に設えられます。
直径2尺2寸(約67cm)の大型の円座で、
編み方は渦巻きです。
職方の手仕事で、一枚ずつ丹精に編み上げらた、
渦巻きの曲線に手業の美しさが感じられます。


カテゴリー: 神具, 祭具 | コメントは受け付けていません。
2013年10月12日 by sporder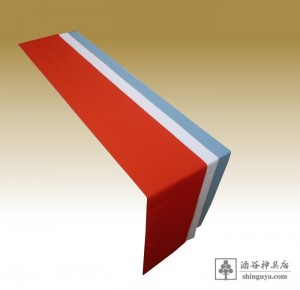 ブログNo.1164
ブログNo.1164
鈴緒 綿サージ 三色
布鈴緒をお仕立てしました。
拝殿前に設えられます。
全長 230cm、幅36cmの袋縫い仕立てです。
生地は厚めの綿サージで、赤、白、水色の三色仕様です。
布鈴緒の色の組み合わせには、決まりはありませんが、
紅白の二色、赤白青の三色、紫白赤黄黄緑の五色の組み合わせが多いです。
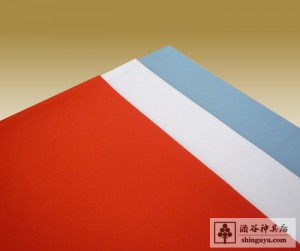
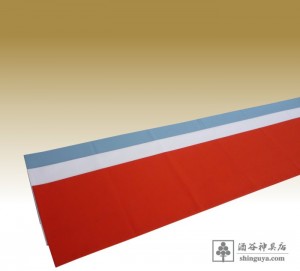
カテゴリー: 神具, 祭具 | コメントは受け付けていません。
2013年10月9日 by sporder ブログNo.1161
ブログNo.1161
八脚案(神饌台、八足台) 木曽桧製 

八脚案(神饌台、八足台)を製作しました。
ご家庭の神床に設えられます。
幅91cm、奥行き18cm、高さ30cm、
材質は木曽桧材です。
通常八脚案は、天板の裏側に溝を掘り込み、
脚を差し込む蟻差し仕様が標準ですが、
分解収納される場合には、
ねじ式やジョイント金具仕様もございます。
カテゴリー: ご家庭での神様のお祀り, 御霊をお祀りするための神具, 神具, 祭具, 八脚案、神饌台、八足 | コメントは受け付けていません。
 ブログNo.1177
ブログNo.1177