神殿 ・ 社殿
2014年6月28日 by sporder ブログNo.1391
ブログNo.1391
神鏡台 1尺 神鏡台を製作しました。
神殿内の御社の前に設えられます。
直径が1尺(約30cm)の大型のもので
金属製のニッケルメッキ仕様です。
神鏡台の材質は木曽桧材、台の奥行は標準寸法より若干調整しました。
神鏡と神鏡台の大きさは、
据えたときに御社のお扉にバランスよく釣り合うことが、基本となります。


カテゴリー: 神具, 祭具, 神殿 ・ 社殿 | コメントは受け付けていません。
2014年6月26日 by sporder ブログNo.1389
ブログNo.1389
御社 台幅2尺5寸(約75cm) 総桧製
御社を製作しました。
台幅75cm、総高さ100cmの大型の社です。
神殿の内陣寸法に合わせて、台の奥行き、
屋根の奥行きを標準寸法から変更してお作りしました。
御社の内部壁面3面には壁代を設え、
扉には赤色紫布筋の戸帳をお取付いたしました。
内部には、御神座となる八脚案と二重の薄地ふとんを納めております。


カテゴリー: 神具, 祭具, 神殿 ・ 社殿, 御社・御宮 ・御霊舎 | コメントは受け付けていません。
2014年6月24日 by sporder ブログNo.1387
ブログNo.1387
三種の神器 神鏡 8寸
三種の神器の神鏡を製作しました。
拝殿の左右に据えられている真榊に設えられます。
直径8寸(約24cm)の大型の神鏡で、
布は朱地雲柄金襴布、房は朱色平頭より房です。
三種の神器の設え方は、向かって右に神鏡と勾玉、
向かって左に剣を配することが基本となります。


カテゴリー: 神具, 祭具, 神殿 ・ 社殿 | コメントは受け付けていません。
2014年6月21日 by sporder ブログNo.1384
ブログNo.1384
御簾 交織 赤倭錦梅鉢紋入り より房二段染め
御簾をお仕立てしました。
神殿の内陣に設えられます。
幅170cm、丈180cm 、
竹は綿糸表編み、布は交織倭錦、
房は紅白二段染めです。
中に納まる御社と全体のバランスを考慮して、
巻上寸法が36cmになるように、房紐を調整しております。
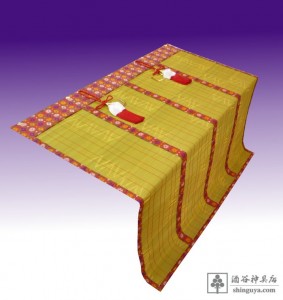
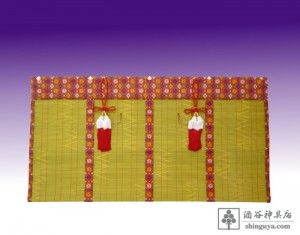
カテゴリー: 神具, 御簾, 祭具, 神殿 ・ 社殿 | コメントは受け付けていません。
2014年6月17日 by sporder ブログNo.1381
ブログNo.1381
御簾 交織倭錦梅鉢紋入り より房三段染め
御簾をお仕立てしました。
神殿の外陣正面に設えられます。
全長455cmの均等3枚割で、左右に長押の出っ張りがあるため、
両端に切り込みを入れております。
竹は綿糸表編み、布は交織倭錦梅鉢紋入り、仕立ては両面仕立て、
房はより房3段染(ブログNo.1374)、
裾には質感が出るようにパイプを巻き込んでおります。
緑系の布に3段染のより房の組み合わせは、雅やかさというよりも、
控えめな中にも格調高さが感じられる組み合わせです。

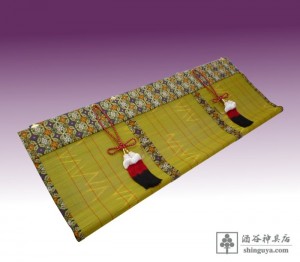
カテゴリー: 神具, 御簾, 祭具, 神殿 ・ 社殿 | コメントは受け付けていません。
2014年6月7日 by sporder ブログNo.1372
ブログNo.1372
壁代 白布 古代小葵地模様入り 196×82cm
壁代を製作しました。
御家庭の神床の三面(側面、後面)に設えられます。
全幅196cm、丈82cm 、
生地は古代小葵地模様入りの白布です。
壁代は、社殿、御社、神床の壁面に設える布の総称です。
仕様も様々で、簡易な白布だけのものから、
赤紫や紫一色の布筋、朽木の摺り柄、飾紐が入ったものなど、
多様な組み合わせがございます。
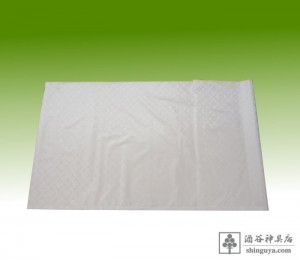

カテゴリー: ご家庭での神様のお祀り, 御霊をお祀りするための神具, 神具, 祭具, 神殿 ・ 社殿, 御社・御宮 ・御霊舎 | コメントは受け付けていません。
2014年6月1日 by sporder ブログNo.1367
ブログNo.1367
御簾房 より房二段染 5寸
御簾房を製作しました。
神殿御簾に設えておられる房のお取り替えです。
房の仕様は、 房頭が二重のより房、紅白二段染です。
御簾を房に付いた鈎(かぎ)で巻き上げる場合は、
揚巻の結びまでの寸法を指定して製作しますが、
今回は御簾の丈が短く鈎で巻きあげない設えのため、
紅白の染分けまでの寸法(33cm)をご指定頂いて製作しました。
より房には二重頭と平頭がございますが、
二重頭は房全体がより格調高く見える上質の仕上げとなります。


カテゴリー: ご家庭での神様のお祀り, 御霊をお祀りするための神具, 神具, 御簾, 祭具, 神殿 ・ 社殿 | コメントは受け付けていません。
2014年5月30日 by sporder ブログNo.1365
ブログNo.1365
三種の神器 剣 1尺5寸(約45cm)
三種の神器の一つの 剣を製作しました。
全長1尺5寸(約45cm)の大型の剣で、
神殿内の左右に配された真榊に設えられます。
生地は雲柄の金襴布で、朱色の平頭より房紐で結び上げています。
布と房紐が赤朱の同色系で、晴れやかさが感じられます。
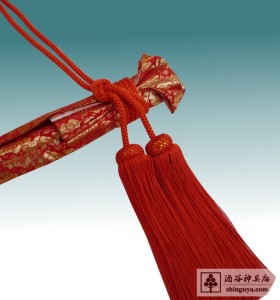

カテゴリー: 神具, 祭具, 神殿 ・ 社殿 | コメントは受け付けていません。
2014年5月28日 by sporder ブログNo.1363
ブログNo.1363
御簾 交織倭錦 麻房三段染め 95×99cm
御簾をお仕立てしました。
社殿内に二枚並べて設えられます。
幅95cm、丈99cm、竹は綿糸表編み、
布は交織倭錦、房は麻房三段染めです。
交織の倭錦は二種類あり、
今回は濃い赤系の交織布でお仕立ていたしました。
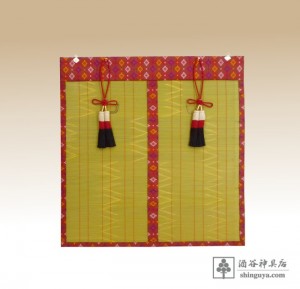
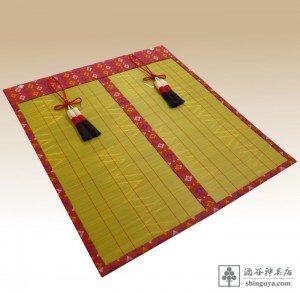
カテゴリー: ご家庭での神様のお祀り, 神具, 御簾, 祭具, 神殿 ・ 社殿, 御社・御宮 ・御霊舎 | コメントは受け付けていません。
2014年5月22日 by sporder ブログNo.1357
ブログNo.1357
擬宝珠 (ぎぼし) 本金メッキ 3寸
擬宝珠をご用意しました。
社殿の改修に伴い、
高欄の金具をお取り替えされます。
全長3寸(約9cm) 表面を本金メッキで仕上げております。
改修された社殿に、擬宝珠や扉金具、海老錠、六葉、唄等が取り付けられると、
一層の神々しさが感じられるように思います。

カテゴリー: 神具, 祭具, 神殿 ・ 社殿 | コメントは受け付けていません。

 ブログNo.1381
ブログNo.1381